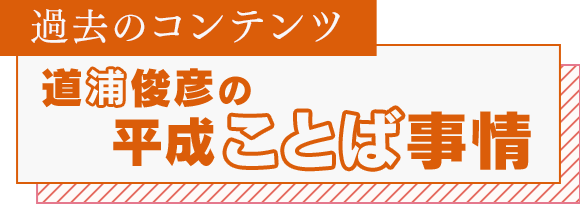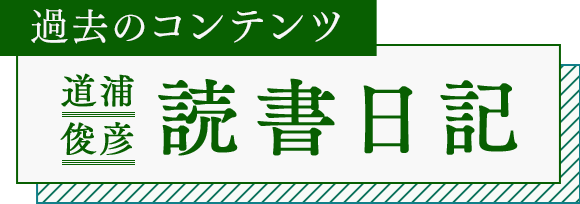電車に乗ろうと並んでいたら、電車が来てドアが開いた瞬間に、私の横からスーッとドアのほうへ近づくおばあさんがいました。
「あ、『横入(はい)り』だ!」
と思ったので、
「並んでるんですよ。ちゃんと順番、守りなさいよ。見えてるんでしょう!」
と注意しましたが、あまり反応がない。聞こえていないのかもしれません。
そのことをフェイスブックに書いたら、関東の友人から、
「『横はいり』って、『順番抜かし』のことだよね?初めて聞いた。新鮮!」
という反応が。
え?そうなのてっきり「標準語」かと思ってた!「関西弁」なのか?
調べてみましょう。
「横入り」 =44万9000件
「順番抜かし」= 3万9100件
ということで、「順番抜かし」の10倍以上「横入り」は使われていました。
その中のサイトの一つには、こう記されていました。
「列への割り込みを意味する『横入り(よこはいり)』は、実は意外と新しい表現で、載っていない国語辞典も珍しくないもよう。一説によると『1980年代、神奈川県で使われていた方言。その後、東京都内にも広まり、全国的に使われるようになった』とのこと。さらに『神奈川県以前から、東海地方(特に愛知県)で使われていた』と説明されている場合もある。国立国語研究所の調査(首都圏大学生の言語使用と言語意識の地域差に関する調査)によると、2012年時点で『横入り』を使う人は43%(296人)、聞いたことがある人は29%(203人)、聞いたことがない人が28%(193人)。『横入り』は、新聞やビジネス誌などにも使われるメジャーな表現になっていますが、まだ“誰もが知っている・使っていて当たり前の共通語”と言い切るのは、ちょっと厳しいかもしれません。」
普通に使われているけど、
「みんなが当然知っている言葉ではない」
のか。しかも東海地方(愛知県)で使われていたとか。私は小学校に上がるまでの5年ほどは「名古屋(と近辺)」に住んでいたので、子どもの頃にそこで身についた言葉かもしれませんね。
『三省堂国語辞典・第八版』を引くと、
*「よこはいり(横入り)」=【愛知・神奈川などの方言】横から列に割こむこと。横ぬかし。
とありました。さすが「三国」!やはり「方言」か。恐らく、愛知・神奈川の人にとっては「気付かない方言」
だと思います。本当に普通に使うよ!
『新明解国語辞典・第八版』は、
*「よこはいり(横入り)」=「(もと、東海地方・神奈川の方言)並んでいる人たちの列に横から割り込むこと。(例)レジ待ちで横入りされた」
『新明解』は、
「もと、方言」
と、「すでに、方言ではない」立場ですね。しかも「愛知」だけでなく「東海地方」と、範囲を広げて捉えている。
『明鏡国語辞典・第三版』は、
*「よこはいり(横入り)」=「【俗】横から無理に入り込むこと。割り込み。(例)行列に横入りする。」
として「方言」とは書かれず「俗語」の記号が付いていました。
『広辞苑』(「第六版」ですが)も、
*「よこはいり(横入り)」=「列に割り込んで入ること。」
とシンプルで、「方言」には触れていませんでした。
その後、その友人から、
「『横はいり』は普通に使われている言葉なんだね。知らずに失礼しました。」
というメールが届きました。いえいえ、やっぱり広く使われているけど「方言起源」のようです。
あ、ついでに「多いい」を聞いた「大井さん」(東京・下町出身)に、
「『横入り』って言葉、使いますか?」
と聞いたところ、
「うーん、聞いたことはあるし、意味も分かるけど、あんまり 使わないですねえ。子どもの頃は『ずる込み』って言っていたなあ」
・・・「ずる込み」!
初めて聞きました。これはまた、別の機会に。